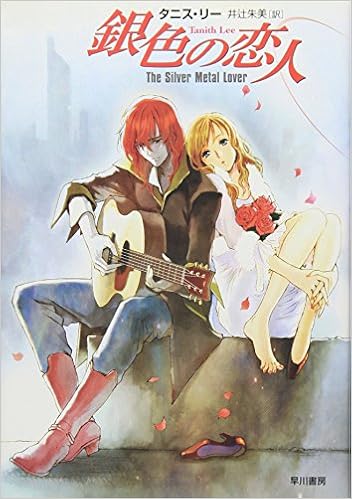オリヴァー・サックス「妻と帽子をまちがえた男」 晶文社 p82-p83 |
ジミーという男性は、コルサコフ症候群という病気のために、ものごとを数秒も覚えていられない。そのため時間の流れのなかで自分を見失い、秒刻みにバラバラになっていく支離滅裂な人生を送っていたのだが、宗教的感動や芸術の中では、人格的なまとまりと人生のリアリティを取り戻し、病気から解放されるという。
脳の異常のために失いかけていた自己や人生を、芸術や宗教のなかでのみ取り戻すことができるということを、どう受けとめればいいのだろう。それは誰の人生(脳)にも保証されている最後の救いと考えていいのだろうか。それとも、それすらもやはり、不幸中の幸運に恵まれた人にのみ許される特権なのだろうか。
************************************
知的な成長の期待できない障害児には、「芸術」でもあてがっておけ、ということを、安易に口にする人は多い。
私はそういう考え方には反発を感じる。
おそらくは周囲から指示されて、「障害者の芸術作品を展示する」ためだけに描かされたと思われる絵画などを見ると、心が寒くなる。それをまた「障害者の製作物だから」という理由でスポットライトを当てて、もてはやすのを見ると、物も言えない気持ちになる。
私も人の親であるから、そうした製作物を批判する言葉が、誰のどんな心を突き刺すものであるのかも承知している。
けれども敢えて言いたい。そのひとの人生は本当に、ベニヤ板に濁ったペンキをなすりつけただけのものなのか、と。誰か、言葉を話さない製作者のかわりに、彼の人生をよく知っているはずの人が、「この人の心にあるものは、いまここでは表現しきれないほど、豊かですばらしいものです」と、声を大にして、言いたくはならないのだろうか。
ジムがコルサコフ症候群から解放されたのと同じように、できることなら、すべての知的障害者を障害から解放するような芸術が存在してほしいと思う。そういうことを望まずに、障害者に芸術を「あてがう」という行為を、やはり私は拒否したい。
※2016年2月11日追記……ずいぶん青いことを書いていたなあと、反省。